
1.未払いの養育費を請求したいと思ったらまず確認しましょう
確認すべきこと
- 取り決めの有無について
- 取り決め内容について
- 成年年齢引下げの影響は?
- 消滅時効について
取り決めの有無について
養育費の支払いを相手に求めるには、裁判所の調停調書や審判書、執行認諾付の公正証書などの公的文書(債務名義)が必要になります。口頭のみの約束では法的強制力がないため、早めに調停手続や公正証書の作成を検討しましょう。
-

-
公正証書がある場合の養育費の請求の仕方
すでに公正証書や調停書、審判書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。 養育費を強制執行する方法 養育費は、借金の返済や慰謝料の請求とは違い、強制執行することが ...
続きを見る
-

-
口約束しかしていなかったときの対処法
離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともありますよね。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケースや養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど様々です。 口約束 ...
続きを見る
取り決め内容の確認
金額・支払期間・支払方法などを把握し、公正証書があれば執行認諾条項付きかどうか確認します。合意内容と現状が合わない場合は、家庭裁判所での見直し手続(履行命令や再調停等)も考慮します。

▼全国の家庭裁判所一覧はこちらから 養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなけれ ... 続きを見る

全国の家庭裁判所一覧
成年年齢引下げの影響
令和2年の成年年齢引下げにより18歳で成年になりますが、既存の取り決めは従来どおり有効です。たとえば「20歳まで」と決まっていれば、新たな手続なしに支払いを継続します。
消滅時効になっていませんか?
養育費請求権の消滅時効は、裁判上で確定した養育費は確定日から10年、それ以外(約束のみ等)は権利行使可能と知った時から5年です。時効が成立すると請求不可となるため、手続きを早めに開始してください。
-

-
未払いの養育費を請求するにあたり時効があります
養育費が請求できる期間には限りがあるのをご存じですか? 養育費の支払額や支払期日について具体的な取決めがある場合、時効の問題が発生しますので、十分に気をつけましょう。 未払いの養育費を請求できる期間に ...
続きを見る
2. 相手方の情報を把握しましょう
-
連絡先・居所確認:元配偶者の現住所・電話・メールなどを確認します。住民票・戸籍の附票で転居先を調べたり、訴訟記録や税務資料(源泉徴収票)で勤務先を把握します。SNSや知人を通じた情報収集もしておくと良いでしょう。
-
資産状況の把握:給与債権や預貯金、不動産など差押え可能な財産を想定し、情報を集めます。勤務先名・金融機関口座・所有不動産の住所などを調査します。令和2年の民事執行法改正で、家庭裁判所を通じて相手方の預貯金口座や勤務先、不動産情報を取得できる手続きも利用可能です。
3. 話し合いによる解決
- 直接交渉:まずは元配偶者と連絡を取り、未払いの理由や支払可能な額・方法について話し合います。内容証明郵便で督促状を送付するのも有効です。話し合いの記録ややり取りは証拠として保管しましょう。
-

-
養育費を払わない元夫に内容証明を送る
元夫から急に養育費の支払いが止まった、何か月も養育費の未払いが続いている…などと困っている方はいませんか? でも、元夫と顔を合わせたくない、養育費を払ってもらわないと困る…そう悩んでいる方は多いことで ...
続きを見る
-
- 支払計画の提案:分割払いの提案など、柔軟な返済計画を提示して合意を目指します。元配偶者が協力的であれば、今後の支払い方法や口座振替設定も検討します。
- 専門家同席:話し合いが難しい場合は、弁護士や裁判所の家庭問題相談室を利用したり、互いに納得できる形での調停申立てを提案します。円満解決が難しいときは法的手段を示唆しつつ慎重に進めます。
\24時間LINEで無料相談できます!/
4. 家庭裁判所への申し立て
-
履行勧告の申立て:既に調停調書等で決まった養育費の場合、家庭裁判所に対し履行勧告を申し出ます。家庭裁判所が調査の上、支払義務者に支払い勧告をします(費用は不要です)。ただし命令ではなく任意的勧告なので、従わない場合は強制力がありません。
-
履行命令の申立て:履行勧告でも支払われない場合、同じ家庭裁判所に履行命令を申し立てられます。裁判所が一定期間内に支払うよう命じ、違反時には10万円以下の過料を科すことができます。この手続も費用はかかりませんが、実際の強制執行手段ではありません。
- 公正証書作成支援:公正証書がない場合、市区町村による証書作成支援制度を利用できる自治体もあります。公証役場で公正証書を作成すると将来の強制執行が容易になります。詳しくは自治体窓口に問い合わせましょう。
-

-
各自治体が行っている養育費確保の支援事業
養育費の保証料を自治体が負担または助成しています 自治体によっては、養育費の保証料を補助金・助成金として支援しているところがあります。2023年12月の時点で実施を行っている自治体は以下のとおりです。 ...
続きを見る
-
-
申立て先:いずれの申し立ても、養育費の決定をした家庭裁判所に行います。新たに子の戸籍謄本や婚姻届出の写し、収入資料等が必要な場合もありますので、事前に家庭裁判所に問い合わせると安心です。
5. 強制執行の手続(債権執行)
強制執行には「債権執行」を利用します。以下の要件・手続きをまとめます。
| 必要書類・要件 | 内容・備考 |
|---|---|
| 債務名義の正本 | 調停調書・審判書・和解調書・判決書・執行認諾付公正証書などのことです。これらは家庭裁判所や公証役場で交付を受けることができます。 |
| 執行文/確定証明書 | 判決書・和解調書・公正証書には執行文(執行できる証明)の付与が必要となります。。審判書の場合は確定証明書が必要です。 |
| 送達証明書 | 債務名義が債務者に正式送達されたことを証明する書類。まだ送達されていなければ、裁判所に送達申請し証明を取得します。 |
| 申立書 | 地方裁判所所定の「債権執行申立書」が必要です。所在地管轄は差押財産により異なり、給与・預貯金なら債務者住所地の地裁、不動産なら所在地の地裁です。 |
| 収入印紙・郵便切手 | 申立手数料は4,000円分の収入印紙が必要です。さらに申立て先の地裁所定額の郵便切手(第三債務者1名あたり約3,000円程度)を同封します。 |
| 第三債務者資格証明 | 差押対象が会社の給与や預貯金の場合、当該会社・金融機関の商業登記事項証明書または代表者事項証明書を添付します。 |
| 住所・氏名変更証明 | 債務名義記載と現住所氏名が異なる場合、住民票・戸籍附票などで両者のつながりを証明します。 |
-
申立ての流れ:上記書類を揃えて裁判所に申立書を提出します(窓口でも郵送でも可)。不備がなければ裁判所は差押命令を発付します。
-
差押効力:裁判所が差押命令を債務者および第三債務者(勤務先や金融機関)に送達した時点で、差押えの効力が発生します。給与の場合、手取りの2分の1までしか差し押さえできません。差押成立後、債務者は会社から給与を受け取れず、会社も債務者に支払えなくなります。
-
取立て(回収):差押命令送達後1週間経過すれば、債権者は第三債務者(会社・銀行)から差押債権の回収を行えます。給与の場合は会社に連絡し支払方法を指示、預貯金なら金融機関に取り立て請求します。将来の給与も併せて差し押さえている場合、以後継続的に支払いを受けることができます。取立てに成功したら、裁判所へ取立届を提出して報告します。
-
費用・期間:手数料は収入印紙4,000円、切手数千円程度。申立から命令発付までは通常数週間以上要し、命令送達から取立てまで合わせて数ヶ月かかる場合があります。勤務先や金融機関が支払いに応じない場合の対処策も検討が必要です。
6. 相談窓口・支援機関
-
-
法テラス(日本司法支援センター):養育費問題の無料法律相談や、低所得者向けの弁護士費用立替制度(民事法律扶助)があります。不安な時はまず法テラスに電話相談しましょう。
-
養育費等相談支援センター:子ども家庭庁が設置した相談窓口で、電話・メールで相談可能です。法律以外の相談も幅広く受け付けています。
-
地方自治体・ひとり親家庭支援:市区町村の母子家庭等就業・自立支援センターや福祉課にも相談員が配置されており、養育費相談員に相談できます。公正証書作成支援や保証制度、各種福祉制度の案内もしてくれます。
-
弁護士会・法律相談:各地の弁護士会が実施する無料法律相談や、信頼できる弁護士への相談も検討します。家庭裁判所の「家事相談」も、離婚・養育費に関する一般的な助言を受けられます。
\24時間LINEで無料相談できます!/
7. 注意点
-
時効に注意:前述のとおり、請求権の消滅時効に留意し、速やかに手続きを進めます。時効完成後は未払い分の請求ができなくなります。
-
証拠保全:養育費の合意・支払いに関する証拠(公正証書・調停調書、銀行振込記録、給与明細、メール・LINEの記録など)はしっかり保存します。口頭約束だけでは強制執行できないため、証拠書類を整えておくことが重要です。
-
記録の重視:履行勧告や差押え申立ての際には、申立人が扶養者であることを示す戸籍謄本などが必要です。また、手続の進行状況や相手の連絡先変遷は逐次メモします。
-
その他:相手が任意支払を再開する場合の手続(履行命令取消申立等)も視野に入れつつ、強制執行前に合意成立で手続終了できれば負担が減ります。また、手続中は感情的にならず、必要に応じて専門家の助言を仰ぐと良いでしょう。
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
養育費は、子どもが安心して生活していくために不可欠なお金です。未払い養育費の回収には、専門的知識と手間が必要です。最新の制度や実務慣行を踏まえ、上記ステップを着実に進めることで回収の可能性を高めてください。本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。
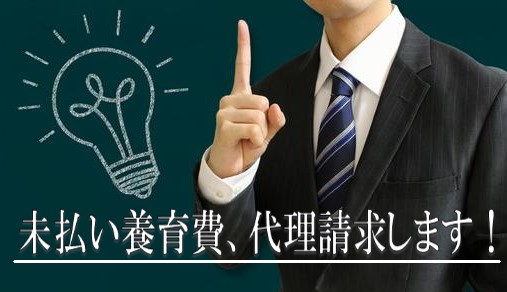
-